トピックス① 鼻づまりがあると勉強・運動・仕事の成績悪化!
トピックス② アレルギー性鼻炎は仕事の生産効率を悪くする!
トピックス③ 鼻づまりと勉強・スポーツについてのQ&A
トピックス④ 生活・睡眠リズムと免疫についてのQ&A
トピックス⑤ PM2.5・黄砂とアレルギー症状についてのQ&A


【花粉症対策特設ページ】はこちら
アレルギー性鼻炎(花粉症)
― つらい症状、早めの対策で軽くできます ―
◆ こんな症状ありませんか? ◆
✔ 朝のくしゃみ・鼻水が止まらない
✔ 鼻づまりで眠りが浅い
✔ 薬を飲んでも毎年つらい
✔ 花粉の季節は仕事や勉強に集中できない
花粉症は、「毎年我慢する病気」ではありません。
早めの対策で症状はかなり軽くできます。
このページでは、 症状の原因・今日からできる対策・治療の選択肢を耳鼻科医の立場から分かりやすく解説します。
◆ 薬だけに頼らない!日常でできるセルフケア(重要)
季節性のアレルギーでは、「予防投与(症状が出る前からの服薬)」が有効です。早目の対策開始がおススメです。
もちろん、薬に頼るだけでなくセルフケアも大切ですので、以下の日常の注意ポイントを参考にして下さい。
-
花粉情報をまめにチェックする(大量飛散の日は屋外での活動を控える)
-
マスク/ゴーグルなどのグッズを活用する
-
掃除をこまめに行い、室内の湿度を適度に保つ(屋内に花粉を持ち込まない対策も)
-
ストレスをためず、十分な睡眠をとる(寝不足・体調不良があると確実に症状が悪化します)
-
風邪をひかないように注意する
-
お酒・タバコを控えめにする(粘膜刺激で過敏性が強くなります)
本特設ページ下部にある「花粉症関連記事・ブログ」も是非参考にして下さい。役立つ情報が満載です。
◆ 鼻づまり放置はNG!口呼吸にも注意
鼻づまりが続くと口呼吸になり、のどの炎症や感染を起こしやすくなります。
喘息のある方では発作の引き金にもなるため注意が必要です。
👉 関連記事もどうぞ
◆ 花粉症セルフチェック
― あなたの症状タイプは?(30秒チェック)―
当てはまる項目にチェックしてみてください。
✅ Aタイプ:くしゃみ・鼻水タイプ
□ 朝起きるとくしゃみが連続で出る
□ 水のような鼻水が止まらない
□ ティッシュがすぐなくなる
□ 外出すると症状が悪化する
👉 花粉やハウスダストに強く反応するタイプ。抗アレルギー薬や初期治療で楽になることが多いです。
✅ Bタイプ:鼻づまりタイプ(要注意)
□ 片側または両側の鼻がいつも詰まる
□ 口を開けて寝ていると言われる
□ 朝、のどが乾燥している
□ 眠りが浅く、日中眠い
👉 鼻づまり優位タイプです。
放置すると睡眠の質低下・集中力低下・副鼻腔炎につながることがあります。
薬だけでなく、処置や手術の追加を要するケースもあります。
✅ Cタイプ:のど・咳タイプ(意外に多い)
□ のどがイガイガする
□ 咳が長引く
□ 花粉時期だけ咳が出る
□ 風邪ではないのに咳が続く
👉 花粉によるのど・気道アレルギー症状の可能性があります。「風邪が治らない」と受診される方の中にも多く見られます(Bタイプとの合併が多い)。
✅ Dタイプ:目・顔症状タイプ
□ 目が強くかゆい
□ まぶたが腫れる
□ 顔や鼻の奥がかゆい
□ コンタクトがつらい
👉 眼症状が強いタイプです。点眼など治療の追加で改善を目指します。
◆ 2つ以上当てはまる方へ
花粉症は多くの場合、複数の症状タイプが同時に出ます。
症状に合わせて治療を調整すると、毎年のつらさをかなり軽くできます。
◆ こんな場合は受診をおすすめします
✔ 市販薬が効かない
✔ 鼻づまりで睡眠の質が悪い
✔ 毎年症状が悪化している
✔ 仕事・勉強に影響している
早めの治療開始が症状軽減のポイントです。


左図:正常鼻腔内
右図:アレルギー性鼻炎の鼻腔
(粘膜が腫れて水様性鼻漏が観察されます)
◆ 鼻アレルギー(花粉症)とは? ◆
同じアレルギーでも、
・気管支 → 喘息
・皮膚 → アトピー
・鼻 → 鼻アレルギー
として現れます。
主な症状は、くしゃみ・鼻水・鼻づまりであり、ひどい場合は頭痛や微熱を伴い、風邪と区別がつきにくいこともあります。
また、アレルギー性鼻炎の中で花粉が原因のものを「花粉症(季節性)」と呼びます。
主な原因花粉:スギ・ヒノキ・イネ科・ブタクサ など
実は真冬以外、ほぼ一年中何らかの花粉が飛散しています。
さらに、ダニ・ハウスダスト・カビ・ペットによる通年性アレルギーもあります。
◆ 原因を知ることが第一歩
鼻アレルギー対策の基本は原因となる物質(抗原)を避けることですが、この対策を有効にとるためには自分のアレルギーの詳しい原因を知っておく必要があります(採血による「特異IgE抗体検査」で原因を特定できます:当院にて実施可)。
例えば、スギ花粉症がある人の半分以上はヒノキやイネ科の花粉・ハウスダストにも反応することがわかっています。そうなると、春先だけ注意していても不充分、ということになってしまうのです。
◆ 治療の選択肢
・日常生活上の対策
先にお示しした「薬だけに頼らない!日常でできるセルフケア」が基本になると考えて下さい。
いくら薬を使っていても、日常のケアが不十分だと治療効果は半減してしまいます・・・。
・内服薬/点鼻薬/目薬
上に示した花粉症のタイプによって適切な薬剤を選択して処方します。
複数ある薬は「強い・弱い」と言うよりも「合う・合わない」と考えた方が良いと思います。
1種類の薬でコントロールできる人、花粉ピーク時に追加の薬を使う人、初めから複数種類の薬が必要な人・・・。
さらに、点鼻薬・点眼薬を併用するのが望ましい人など。
個人個人の状態に合わせて、カスタムメイドの処方を行うのが理想的です。
・日帰りでできる粘膜処理術
症状が強い場合には、鼻の粘膜(下鼻甲介)を高周波メスまたは薬剤で処理する日帰り手術を行うことがあります。
くしゃみ・鼻水・鼻づまりの軽減が期待できますが、アレルギー自体が治るわけではありません。
手術時間は10~15分ほどで、局所麻酔のみで可能です。経過により2〜3回の追加処置が必要なこともあります(当院で実施可)。
・病院紹介の上で受ける鼻の手術
さらに症状が強い方、日帰り手術でも症状コントロールが上手くいかない方の場合、病院紹介の上で入院での鼻手術を検討するケースもあります。
・舌下免疫療法について
スギ花粉・ダニに対する舌下免疫療法という治療法もあります。
当院では実施していませんが、希望される場合は対応医療機関への相談をおすすめします。
◆ まとめ
鼻アレルギーは「慢性的な不快感」だけでなく、集中力の低下や睡眠の質にも影響します。
原因をしっかり調べ、体に合った治療とセルフケアを続けることが大切です。
症状が長引くとき/繰り返すときは、早めのご相談をおすすめします。
❓ 花粉症 Q&A― 患者さんからよくある質問 ―
Q1.花粉症の薬は、いつから飲めばいいですか?
A.症状が出る前、または出始めに飲み始める方が効果的です(理想は花粉飛散開始前)。
症状が強くなってからでは、薬が効くまで時間がかかることがあります。
毎年つらい方は、花粉飛散前からの「初期治療」がおすすめです。
Q2.市販薬で様子を見ても大丈夫ですか?
A.軽症であれば市販薬で対応できることもあります。
しかし、効きが悪い・眠気が強い・毎年悪化する場合は、薬の種類や治療方法を調整することで楽になるケースが多くあります。
Q3.花粉症は年齢とともに治りますか?
A.軽くなる方もいますが、悪化する方もいます。
また、鼻づまりが強くなる・副鼻腔炎を繰り返す・咳やのど症状が増えるなど、症状のタイプが変わることもあります。
Q4.鼻づまりだけでも花粉症ですか?
A.鼻づまりだけが強く出るタイプもあります。
このタイプは睡眠障害・口呼吸・日中のだるさにつながりやすく、治療調整で改善を目指す必要があります。
Q5.毎年同じ薬を飲んでいますが、変える必要はありますか?
A.症状が十分コントロールできていれば同じ薬で大丈夫ですが、症状や生活環境の変化により、薬の調整・変更が必要なことがあります。
「去年効いた薬が今年効かない」という相談は珍しくありません。
Q6.花粉症で受診するタイミングは?
A.症状が軽いうちの受診が最も楽です。
症状が強くなってからよりも、薬が効きやすい・悪化を防げる・通院回数が少なく済む・強い薬を飲むリスクを減らせるメリットがあります。
■ 症状が続く/気になる場合はご相談ください
✔ 鼻づまり・のどの痛み・耳の違和感など専門的に診療しています。
✔ 当日予約にも対応しています。
👉 診療案内は こちら
👉 初診患者さんのWEB予約は こちら
■ その他の花粉症関連記事・ブログ:さらに詳しく知りたい方へ
・ 花粉飛散は早まっている?2026年の傾向と早めの花粉症対策を耳鼻科医が解説
・ 花粉症と雨の関係
・ 花粉症・感染症対策で有効なマスクは?
・ 花粉症なのに“のどが痛い・咳が出る”のはなぜ?原因と対策を解説

口腔アレルギー症候群(OAS)/花粉・食物アレルギー症候群(PFAS)
口腔アレルギー症候群(Oral Allergy Syndrome:OAS)は、花粉症のある方に多くみられる食物アレルギーの一種です。
花粉に含まれるアレルゲンと、果物や野菜に含まれる成分の構造がよく似ているため、体がそれらを「同じもの」と誤って認識してしまい、特定の食べ物を食べた直後にアレルギー症状が起こります。
医学的には、このような病態全体を花粉・食物アレルギー症候群(Pollen-Food Allergy Syndrome:PFAS) と呼び、OASはその中で最もよくみられる症状の現れ方です。
■ どんな症状が出るの?
原因となる食べ物を食べてから数分以内に、次のような症状が現れます。
-
口の中や唇のかゆみ
-
のどのイガイガ感
-
唇や口の軽い腫れ
-
口の中のピリピリ・チクチクした違和感
多くの場合、症状は口やのどに限局し、短時間で自然に治まるのが特徴です。
一方で、まれではありますが、全身のじんましん、息苦しさ、強いのどの腫れなどを伴うこともあるため、「軽い症状だから大丈夫」と自己判断せず、注意が必要です。
■ なぜ口の中だけで起こりやすいの?
PFASの原因となるアレルゲンは、熱や消化に弱い性質を持っていることが多く、食べてすぐに触れる口やのどで反応が起こりやすいと考えられています。
そのため、
-
生の果物や野菜では症状が出る
-
加熱すると症状が出にくい
(例:生のりんごは症状が出るが、アップルパイは大丈夫)
といったケースがよくみられます。
■ 花粉と食物の「交差反応」
口腔アレルギー症候群は、花粉と食物のアレルゲンの“似ている部分”による交差反応が原因です。
たとえば、特定の花粉にアレルギーを持つ方が、それと似た構造を持つ果物や野菜を食べた際に、体が同じアレルゲンだと誤認して症状を起こします。(※代表的な組み合わせは下表をご参照ください)
■ 対処・治療について
① 原因となる食べ物を「生」で避ける
OASでは加熱すると症状が出にくくなることが多く、無理に完全除去せず、食べ方を工夫することで対応できる場合があります。
② 花粉症の治療を行う
花粉症の症状が強いほど、OAS/PFASの症状も出やすくなる傾向があります。
抗アレルギー薬、点鼻薬、舌下免疫療法などが症状軽減に役立つことがあります。
③ 症状が強い場合は医療機関へ
-
口やのどの腫れが強い
-
症状が毎回悪化している
-
口以外の全身症状が出る
このような場合は、早めに医療機関を受診してください。
全身症状がある場合は、救急受診が必要になることもあります。
■ 最後に
口腔アレルギー症候群は、花粉症と深く関係したアレルギー反応です。
「花粉症がある」「果物や野菜で口がかゆくなる」といった症状がある方は、自己判断せず一度ご相談ください。
必要に応じて食物アレルギーの専門医への紹介を検討する場合もあります。


◆ 局所性アレルギー性鼻炎 ◆
ー 採血では異常が出ない ー
「くしゃみ・鼻水・鼻づまりがあるのに、アレルギー検査では異常なし」と言われたことはありませんか?
実は、そんな方の中に“局所性アレルギー性鼻炎(local allergic rhinitis:LAR)”というタイプの鼻炎が隠れていることが分かってきました。
🔹 検査で分かるタイプと分からないタイプ
アレルギー性鼻炎は、大きく2つに分けられます。
-
アトピー型アレルギー性鼻炎:
採血でIgE抗体が上昇し、アレルギー反応が確認できるタイプ。 -
非アレルギー性鼻炎:
採血ではアレルギー反応が見られないタイプ。
しかし最近の研究で、この「非アレルギー性鼻炎」の中に、
**血液中ではIgE抗体が検出されないのに、鼻の粘膜で局所的にIgEが作られているタイプ(=局所性アレルギー性鼻炎)**があることが分かってきました。
🔹 症状はふつうのアレルギー性鼻炎と同じ
局所性アレルギー性鼻炎の方は、花粉やホコリなどのアレルゲンにさらされると、
-
くしゃみ
-
水っぽい鼻水
-
鼻づまり
といった典型的なアレルギー性鼻炎の症状が現れます。
つまり「検査では異常なし」でも、実際にはアレルギー反応が起こっているケースがあるのです。
🔹 研究で分かったこと
兵庫医科大学の研究では、
アトピー素因のないマウスでも、アレルゲンを鼻から吸入させ続けると、
1️⃣ 鼻の粘膜だけでIgE抗体が作られ、鼻炎症状が出る
2️⃣ その状態が続くと、やがて全身のアレルギー反応(アトピー型)へ進行し、喘息を合併する
という結果が報告されています。
これは、人間の局所性アレルギー性鼻炎からアトピー型アレルギー性鼻炎、そして喘息へと進行する経過に非常によく似ています。
🔹 まとめ:早めの対応が大切です
局所性アレルギー性鼻炎は、現時点では採血などで確定診断することが難しい疾患です。
それでも、「アレルギーが疑われる症状」がある方は、花粉やホコリなどの原因物質をなるべく避けることが大切です。
症状が長引く、または季節の変わり目に悪化する方は、耳鼻咽喉科で一度相談してみましょう。
早期の対応が、重症化や喘息の予防につながります。
関連記事がブログに掲載されています(こちら)
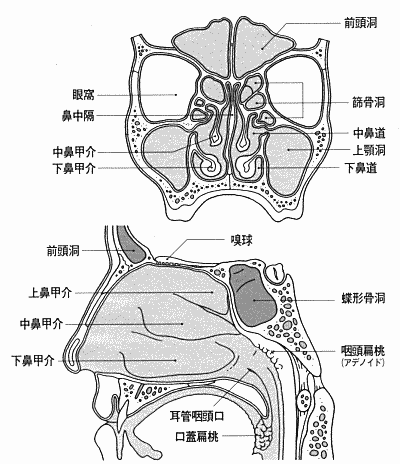
鼻からつながる空洞部分
(前頭洞、篩骨洞、上顎洞)
これらを副鼻腔といいます


<正常の副鼻腔>
副鼻腔には含気があり黒く写る

<副鼻腔炎のCT>
右副鼻腔(画像では左)に炎症所見を認める
◆ 慢性副鼻腔炎 ◆
― 長引く鼻づまり・鼻水・嗅覚の低下 ―
「鼻炎」と「副鼻腔炎(ふくびくうえん)」、名前は似ていますが、実は起こっている場所が少し違います。
鼻の中だけで炎症が起きている状態が鼻炎、
炎症が鼻の奥にある「副鼻腔(鼻のまわりの空洞)」まで広がった状態が副鼻腔炎です。
● 副鼻腔炎の種類
-
急性副鼻腔炎:かぜなどの感染がきっかけで一時的に炎症が起こるタイプ
-
慢性副鼻腔炎:炎症が3か月以上続くもの
「慢性副鼻腔炎」は、昔から「蓄膿症(ちくのうしょう)」と呼ばれてきた病気です。
感冒などの急性炎症が治りきらない場合、程度にかかわらず炎症が長期間持続した場合などに起こります。
● 主な症状
-
鼻づまり
-
粘り気のある鼻汁(黄~緑色のことも)
-
においが分かりにくい
-
鼻水がのどにまわる(後鼻漏)
-
頭が重い、頬のあたりの痛み
これらの症状が数週間以上続く場合は、慢性副鼻腔炎の可能性があります。
● 原因・発症のきっかけ
風邪(ウイルス感染)やアレルギー性鼻炎などがきっかけで、副鼻腔の通り道(自然口)がふさがり、膿や粘液が溜まって炎症が続いてしまいます。
また、以下のような方は慢性化しやすい傾向があります。
-
アレルギー性鼻炎がある
-
鼻中隔湾曲症(鼻の仕切りが曲がっている)
-
喫煙習慣がある
-
花粉やほこりなどに長期的にさらされている
-
鼻ポリープ(鼻茸)がある
● 治療について
基本は**保存的治療(手術をしない治療)**が中心です。
薬物療法
-
抗菌薬(マクロライド系を少量・長期間使用することも)
-
抗炎症薬・粘液をさらさらにする薬
-
点鼻薬(ステロイドスプレーなど)
処置
-
鼻の中の洗浄
-
吸引による鼻汁除去
-
ネブライザー(霧状の薬で炎症を抑える)
手術(内視鏡下副鼻腔手術:ESS)
保存的治療で改善しない場合、
副鼻腔の通りを広げて換気・排膿を改善する内視鏡手術が選択肢となります。
日常生活での工夫
-
鼻うがいで鼻の通りを清潔に保つ
-
部屋の加湿(乾燥は炎症を悪化させます)
-
アレルギーの管理(花粉やダニ対策)
-
禁煙・睡眠・栄養など、全身の健康を整えることも重要です
合わせて読みたい ⇒ 鼻うがいのメリット・デメリットを耳鼻科医目線で解説します
●まとめ
慢性副鼻腔炎は、鼻づまりやにおいの低下などが長く続く病気で、放置すると嗅覚障害や睡眠の質の低下にもつながります。
「風邪が治っても鼻がスッキリしない」「においがわからない」と感じたら、早めに耳鼻科での診察を受けましょう。
症状の背景には、鼻・のどだけでなく生活習慣や体調全体の影響が関係することもあります。
▶ 耳・鼻・のど・体調管理のQ&A(院長解説)は こちら
ー 上顎癌(じょうがくがん)ー
— 副鼻腔にできる代表的な悪性腫瘍 —
鼻の奥には「副鼻腔」と呼ばれる空洞がいくつかありますが、その中でも上顎洞(じょうがくどう)と呼ばれる頬の裏側に位置する空洞に、まれに上顎癌が発生します。
● 主な症状
上顎癌は進行するまで気づきにくいことがあり、次のような症状が徐々に出てきます。
● 鼻づまり・鼻出血(片側だけ)
● 頬部(片側)の痛み・腫れ、しびれ
● 血の混じった涙・目の周囲の腫れ
● 上の奥歯の痛みや歯が浮く感じ
● 膿のような鼻汁が続く
症状はいずれも “片側だけ” に起こるのが特徴 で、長く続く場合は注意が必要です。
一般的な副鼻腔炎と似ていますが、治療に反応しない片側の症状は、精密検査を考えるサインになります。
● 原因・背景
明確な原因は特定されていませんが、以下が発症に関与すると言われます。
-
喫煙
-
職業性粉じん(木工、革産業など)
-
慢性の副鼻腔炎
-
人によっては遺伝・体質的な要素も
● 診断
上顎癌が疑われる場合、以下のような検査を行います。
-
内視鏡検査(鼻の奥の状況を確認)
-
CT / MRI(周囲の浸潤を評価)
-
組織検査(生検) … 最終診断に必須
-
必要に応じて PET などの画像検査
● 治療
治療は病期により異なりますが、一般的には以下の組み合わせです。
-
手術(腫瘍切除)
-
放射線治療
-
抗がん剤(併用されることも)
早期ほど治療選択肢が広がり、機能や形態をできるだけ温存しやすくなります。
● 受診のタイミングについて
片側だけの鼻づまり・鼻血、頬の痛み・しびれなどは、単なる副鼻腔炎ではない可能性があります。
**「片側だけ」「治りにくい」「症状が徐々に強くなる」**という場合は、早めに耳鼻科での検査をお勧めします。

副鼻腔炎のCTと比べても、その違いは歴然。
頬の外側および眼の中まで腫瘍が進展しています(矢印部)。
鼻の中にも進展し、鼻血の原因になります。
