トピックス② ヨード(イソジン)によるうがいは風邪の予防に無効 ?
トピックス③ インフルエンザにかかりやすいタイプが判明!
トピックス④ 口呼吸と感染症の関係についてのQ&A
トピックス⑤ 生活・睡眠リズムと免疫についてのQ&A
トピックス⑥ PM2.5・黄砂とアレルギー症状についてのQ&A
◆ 急性咽頭炎・扁桃炎
◆ 声帯ポリープ・ポリープ様声帯・声帯結節
◆ 喉頭肉芽腫
◆ 咽頭異物
◆ 舌癌・下咽頭癌
🟩【のど(かぜ・扁桃炎・声の不調・逆流性・後鼻漏)】
のどの症状は日常生活のクセや環境とも深く関係しています。
症状の原因や改善ポイントを丁寧にまとめた記事をご紹介します。
のどの話題に関する院長ブログはこちら
🟫【感染症(インフル/コロナなど感染症・健康管理)】
流行状況・注意点・予防のコツを中心にまとめています。
「受診すべきか迷う…」という時の判断材料にもお使いください。
感染症・健康管理の話題に関する院長ブログはこちら

◆急性咽頭炎・扁桃炎 ◆
—少しの口呼吸がトラブルを招く —
急性咽頭炎・扁桃炎は、ウイルスや細菌による感染が原因で起こり、急な発熱・強いのどの痛み・咳などの症状をもたらします。
乳幼児では、のどの痛みをうまく訴えられないため、よだれが増える・機嫌が悪いといった形で現れることもあります。
● 原因
急性咽頭炎の多くは ウイルス感染が原因(成人で90%前後)。
一方で、細菌性は
-
成人:10%程度
-
小児:15~30% とされます。
-
細菌性の代表が A群溶血性連鎖球菌(溶連菌) で、この場合には 適切な抗菌薬治療 が必要になります。
● 治療で大切なこと
「のどが痛いから抗生剤を!」……実はこの考え方は正確ではありません。
抗菌薬が必要なのは “細菌性の一部の症例だけ”。
ポイントは次のとおりです。
-
必要な症例をしっかり見極めること
-
必要な場合のみ、適切な種類を、適切な期間だけ使用すること
不要な抗生剤は、効き目が弱くなる“耐性菌”の原因にもなります。
● こんな症状は受診をおすすめします
-
高熱が続く
-
のどの痛みが強く食事がとれない
-
首のリンパが腫れて痛い
-
口が開きにくい、よだれが多い(小児)
-
発赤・白苔(白い膿)が扁桃に見える
● 口呼吸は感染の大きなリスク
鼻には、空気の加湿・加温・異物除去という大切な“フィルター機能”があります。
ところが、「少しだけ」「気付いたら」口が開いている状態(口呼吸)が続くと、ウイルスや細菌が直接のどへ入りやすくなります。
-
睡眠中の口の開き
-
朝起きたときの口の乾燥
-
マスク生活で知らずに口呼吸になっている
こうした“ちょっとした口の開き”が、感染のきっかけになることも。
合わせて読みたい ⇒ 口呼吸が招くトラブルと鼻呼吸のススメ
● 予防としてできること
-
のどの乾燥を防ぐ(加湿、こまめな水分)
-
手洗い・うがい
-
睡眠・栄養をしっかり確保
-
鼻呼吸を意識する習慣づけ
-
鼻づまりがある場合は早めに治療


◆ 声帯ポリープ・ポリープ様声帯・声帯結節 ◆
— 「いつも100%の発声」はムリ
だからこそ“日々の使い方”が大切 —
声がかすれる原因として最もよく知られているのが、この 3つの声帯疾患 です。
● 声帯はどうやって声を出すの?
声帯は、左右2枚のヒダでできていて
-
息を吸う時:開く
-
声を出す時:閉じて振動する という動きをしています。
声をよく使う人ほど、この“声帯が擦れ合う回数”が増えます。
この摩擦が続き、粘膜に炎症が起こると 腫れ・水ぶくれ・硬化 といった変化が起きて、声がかれたり、途切れたりするようになります。
● 病変の違い(イメージ)
◎ 声帯ポリープ
…声帯の一部が 水ぶくれのように腫れる 状態
◎ ポリープ様声帯
…炎症が広範囲に及び、声帯全体が ぶよっと腫れる
(喫煙者・声を酷使する人に特に多い)
◎ 声帯結節
…擦れ合う部分が ペンダコのように硬くなる
(保育士・教員・スポーツ指導者・歌手など声を使う仕事に多い)
いずれも、慢性的な声の酷使 が大きな原因です。
● 主な症状
-
声がかすれる、息漏れのある声
-
喉に力を入れないと声が出ない
-
長く話すと声が続かない
-
朝と夕方で声の調子が変わる
-
高い声が出ない(歌手に多い訴え)
● 治療の基本は「声を休める」こと
残念ながら、声帯の腫れを“一気に治す魔法の薬”はありません。
もっと言えば、プロの歌手ですら「常に100%の声を維持する方法」は存在しないと言われています。
そのため治療の中心は
-
沈黙(声の安静)
-
必要に応じて吸入や薬
-
生活習慣の見直し(禁煙・睡眠・水分)
-
声の使い方を整える“音声治療” です。
どうしても声を使う仕事の方は「必要最低限の発声」 を徹底し、声帯の負担を減らすことが必要になります。
● 手術が必要になるケース
-
ポリープが大きく、声がほとんど出ない
-
仕事に支障が大きい
-
数週間の安静でも改善しない
-
ポリープ様声帯で粘膜の腫れが強い
手術といっても、内視鏡下で行う繊細な微細手術で、多くは短期入院です。
● 声を守るためにできること(予防がいちばん大事)
-
こまめに水分をとる(粘膜の乾燥予防)
-
大声・長時間の連続した発声を避ける
-
しゃがれ声のまま無理して話さない
-
湿度を保つ(エアコン・乾燥に注意)
-
喫煙者は禁煙が強く推奨されます
-
“咳払い”を減らす(これも声帯に強い衝撃になります)
声の仕事の方は、ウォームアップ発声・クールダウンを習慣化するだけでも声帯のダメージが減ります。
関連記事がブログに掲載されています(こちら)
下の画像は左から「声帯ポリープ」「ポリープ様声帯」「声帯結節」です。
確かに、この状態では“きれいな声”が出にくいのが想像できますよね。




◆ 喉頭肉芽腫 ◆
喉頭肉芽腫(こうとうにくげしゅ)は、声帯の後ろ側(声帯突起と呼ばれる部位)にできる丸いできものです。
声帯ポリープや声帯結節と同じ「声のかすれ」を引き起こしますが、発生する場所が異なるのが大きな特徴です。
● なぜできるの?(原因)
喉頭肉芽腫は、実は “半数以上が原因不明” とされていますが、以下が代表的な誘因です。
◎ 気管挿管による刺激
手術で全身麻酔を受けた際、気管にチューブを入れることで声帯後方に刺激が加わり、肉芽腫ができることがあります。
◎ 逆流性食道炎(胃酸逆流)
最近増えている明確な原因です。
胃酸がのどの奥まで上がってくると、粘膜が慢性的に荒れ、肉芽腫の形成につながります。
逆流性食道炎を引き起こす要因
-
ストレス
-
加齢
-
アルコール多飲
-
食べすぎ・早食い
-
ベルト・ガードル・姿勢などによる腹圧上昇
胸やけ・胸の痛みといった典型的症状に加えて、のどの違和感・異物感・慢性的な咳なども起こりやすくなります。
◎ 声の酷使
声帯の後ろ側に力が入りすぎる“喉押し発声”を続ける方に多い傾向があります。
● 主な症状
-
声がかすれる(嗄声)
-
のどに何かつまった感じ
-
声を出すと疲れる
-
咳払いが増える
-
痛みは少ないが違和感が続く
● 治療
多くのケースで、薬物治療と生活改善で様子をみます。
-
胃酸分泌抑制薬(PPIなど)
-
ステロイド薬や吸入治療
-
声の使い方の見直し(音声治療)
→ のどの後ろに力が入りやすい発声習慣の改善が有効
-
生活習慣の改善
→ 就寝前の飲食を避ける、アルコール控えめ、腹圧を高めない、など
一定期間治療しても改善が乏しい場合や、飲み込みに影響が出る場合には、手術で肉芽腫を除去することもあります。
(癌化することはきわめて稀とされていますが、長く続く嗄声は必ず評価が必要です。)
下の画像は喉頭肉芽腫の典型例です。
声帯ポリープ・結節と比べて
“声帯の後方にコロンと丸い塊がある” のが特徴です。

◆ 咽頭異物 ◆
「それ、“あーん”って食べて本当に大丈夫?」
のどに何かが刺さったり、引っかかったりした状態を 咽頭異物(いんとういぶつ)と呼びます。
代表的なものは 魚の骨。季節の旬の魚(サンマ・アジ・タイなど)を食べた際に、骨がのどに刺さって来院される方が多くみられます。
● 魚の骨が刺さる場所とその対応
魚骨の 約80%は扁桃(へんとう) に刺さり、この部位なら比較的容易に摘出できます。
しかし、同じ扁桃でも
-
奥側(陰窩の深部)
-
舌の付け根(舌根部)
などに刺さってしまうと、視認が難しく処置が大変になる場合があります。
場合によっては局所麻酔を行ってから摘出する必要もあります。
● 高齢の方で特に注意が必要な“PTP誤飲”
ご高齢の患者さんで時々あるのが、薬のシート(PTP:プラスチックとアルミでできた包装)を 誤ってそのまま飲み込んでしまう ケースです。
PTPは鋭利で、食道や胃を傷つける危険があります。
誤飲してしまった場合は、耳鼻科では対応できないため、内科での消化管内視鏡による摘出が必要となります。
誤飲防止のためにも、薬は必ずシートから出して服用する習慣 を徹底しましょう。
● のどに違和感があるときは無理に飲み込まない
「ご飯を飲み込めば骨が取れる」という民間療法がありますが、むしろ
-
刺さった骨がさらに深く入る
-
のどを傷つける などのリスクがあります。
違和感や痛みが続く場合は、早めの受診をおすすめします。
画像は左が魚骨(鯛)、右がPTPです。気を付けたいですね。
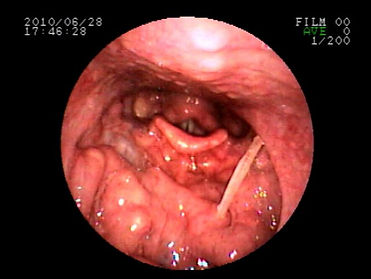

◆ のどの違和感・継続する痛み ◆
ー 下咽頭癌・舌癌 ー
「何だかのどの具合が悪いな…」と放置していませんか?
「のどが詰まった感じがする」
「口の中が何となく変」
こうした症状の多くは軽症で心配のないものですが、まれに重大な疾患が隠れている ことがあります。
脅かすつもりはありませんが、原因がはっきりしない症状が続く時は、念のため注意が必要です。
一般的な健康診断では、のど(咽頭・喉頭)の細かい異常を見つけることは困難です。
耳鼻咽喉科では内視鏡で詳細にチェックできます。
● なかなか治らない口内炎は要注意
下の写真は「舌癌」の一例です。
舌癌の中には、口内炎を繰り返すうちに発症するタイプ があります。
注意すべきポイント
-
長期間治らない口内炎
-
いつも同じ場所に繰り返しできる口内炎
多くの場合、その部位に
-
歯が当たっている(舌の縁に多い)
-
入れ歯や矯正器具が慢性的にこすれている といった背景があります。
さらに
-
飲酒/喫煙といった慢性刺激もリスクになります。
合わせて読みたい ⇒ 同じ場所の口内炎、危険なサインかも?
● 口内炎を起こしやすい人の共通点(原因と対策)
1.歯磨きが不十分
食べかすが残ると細菌が繁殖します。
→ 食後と就寝前の歯磨きを習慣に。
2.強すぎるブラッシング
歯ぐきや頬の内側を傷つけると炎症の原因に。
→ 力を入れすぎず、優しく磨きましょう。
3.口が乾燥しやすい
唾液の抗菌作用が低下します。
→ 口呼吸の癖がある方は特に注意!
4.栄養バランスの偏り
ビタミン不足は粘膜トラブルを誘発します。
→ できる範囲でバランスを意識した食事を。
5.過度の飲酒・喫煙
粘膜への慢性刺激、ビタミンバランスの乱れにつながります。
6.疲労・ストレスによる免疫低下
→ 睡眠・休息をしっかりと。
7.ペットボトル飲料の“じか飲み放置”
一度口をつけた飲料を放置 → 菌が繁殖 → 再飲用で口内環境が悪化します。
● のど〜食道入口にできる「下咽頭癌」にも注意
次の写真の症例は「下咽頭癌」です。
この部位は食道の入り口に近いため、
● 飲み込むときに引っかかる・痛い
● 固形物だけ飲みにくい
● のどの痛みが続く といった症状が特徴です。
水分より固形物が飲みにくい場合は特に要注意です。
● もちろん、怖い病気だけではありません
のどの違和感や痛みの多くは、
● 慢性咽喉頭炎
● 逆流性食道炎(胃酸逆流)
● アレルギー
● 乾燥による刺激 などの良性疾患でも起こります。
しかし「繰り返す」「なかなか良くならない」、といった場合は、一度チェックしておくと安心です。






